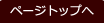全例にできるわけではありませんが、当院ではなるべく初診の時点で詳しい病状とその原因や背景、さらには見通しまでも立ててお伝えするように全力で診察を行っています。(どうしてもわからないことや最初の見立てが違っていることもありますが)
ある程度の治療計画が見込める場合は、どのくらいのスパンで服薬が必要になるかお伝えすることもありました。
最近では、それもちょっとやりすぎだなぁと思う節がありまして、少し落ちついたころにお話ししようと思うようになりました。
たとえば、うつ病の患者さんはとても悲観的な状態で受診されます。それでもご本人はどこかで「受診して治療すれば風邪のようにすぐに治って薬も不要になる」という理想を思い描いていることも少なくありません。
自分がどういう状態なのか、
改善するのか、
それらがわかるだけでかなり安心できることが多いです。
しかし、その先の維持療法の見込みまで言われてしまうと、理想と違っていることで少し落胆してしまいます。
正直に全てをお話しする誠意も大事ですが、お伝えするタイミングも簡単ではありません。
また、初診時に全てを盛り込むと患者さんも理解仕切れないかも知れません。
できれば、患者さんのほうで疑問に思ったタイミングで聞いていただければと思います。
「薬はいつまで飲むのですか?」
答えは「ケースバイケース」です。
うつ病と言ってもそれぞれの背景や特性、生活、置かれた状況など千差万別です。
一般論で論文のデータを提示して説明することは簡単ですが、でもそれって目の前の患者さんに当てはまるの?っていう話です。
初めてうつ病になった人と、2回以上うつ病を繰り返している人では統計的に再発率には差があり維持療法の期間は違ってきます。
それは一般論でもあり、だいたい目の前の患者さんにお伝えしても間違っていないですが、
初回であっても、長めにした方がいい人と、早めに切り上げても良さそうな人もいて、ある程度見通しは立てられることがあります。
発達障害という言葉が知られるようになってから久しくなりましたが、当院では発達障害とまでは言えないまでも非定型発達の部分特性がどのように発症に関連しているのかなど、背景にある要素を詳しくアセスメントしています。
ネックになっている発達特性が、現在の環境でどれだけ支障をきたしているのか、環境が変わる見通しはどうなのか、その辺りまで考えると、維持療法をどれくらい続けるべきか検討する材料になると思っています。
また、服薬の期間と障害の程度は必ずしも一致しません。
「睡眠薬が悪」という風潮がありますが、(薬剤の種類は厳選しますが)ケースによっては年単位で使用した方が良い場合があると思います。
とある大企業の取締役としてご活躍されている能力の非常に高い方が何人か通院されています。
どの方も社会適応は問題ないわけです。
ただ、元々の特性として過集中、過覚醒、マルチタスクの特性があって、かなりのタスクをこなされているわけです。
そういう方は色々な生活習慣を工夫しても、なかなか良い睡眠が取れなかったりします。
「寝れなくても死にはしない」という乱暴な言い方をする人もいますが、睡眠はとても大事な役割があります。
心身の調子を整え、記憶を整理し、脳のゴミを排泄する働きがあります。
脳にゴミが溜まると認知症の発症を加速させます。
治療してでも睡眠をとった方が良いと考えます。
役職定年などのタイミングで減薬して、定年後に(対象喪失のうつ症状がなければ)廃薬に持ち込めることも少なくありません。
長期的な計画ですが、そのようなケースもあります。
漫然と処方を続けるのではなく、ちゃんとビジョンを持って維持療法を行っているのです。