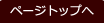前回のブログで仕事量が増えすぎて、毎日綱渡りと書きました。
患者さんにお渡しする書類はなんとか間に合っていますが、
最近カルテ作成が遅れがちで。
今はまた初診の受付を中止にしていますが、
初診はとても大事なセッションだと私は思っています。
せっかく初診のために時間を無理やり作っているのだし、
初診をちゃんとやらなくて、いつちゃんと診るというのでしょうか?という感じで。
症状や病気の内容にもよりますが、複雑性トラウマの方などの病歴は大概混みいっています。
「そんなことある?」と驚くような過酷な生育環境だったりして、話を聞いているとキリがなくなることも。
患者さんの時間前後感覚や記憶も曖昧で、とっ散らかっていることも少なくありません。
というわけで初診に2時間〜2時半かけてしまうことが最近続いてしまって、私もげっそりです。
(2時間もどうやって作っているの??
外来やっている医師なら当然疑問に思うでしょう。
もちろん連続して2時間は確保できません。
前半と後半に分けて、患者さんには休憩を挟んでもらいます。
その間に再診の患者さんを次々と診ていくのです。)
ただ、「話したくないことを無理やり聞かれた」ということにならないように注意しなければなりません。
トラウマについては患者さんの反応を見ながら慎重に伺います。
その前の段階で、「詳しく話したくないという方は当院を受診しないでください」とHPにもしつこく掲示していますし、
電話の段階で秘密主義の匂いがする人やあまり触れられたくなさそうにしている方は、他の機関にご相談していただくように誘導します。
その上で診察しているので、ほとんどの患者さんは率直に話をしてくれます。
まずは患者さんの緊張度合いを見て、雑談から入っていくこともあります。
最初は症状や経過の確認をし、診断のあたりをつけ、徐々にその背景となる生育歴や発達の傾向、家族歴を伺っていきます。
患者さんの言ったことをおうむ返しにしながらカウンセリングするのが基本ですが、私はあえて私が理解した言葉に言い直して患者さんに一つ一つ私の理解があっているかどうか確かめながら先に進めます。
大体前半の段階ではすでに患者さんのテーマを見出しているので、あとは占い師のようになっていきます、笑。
患者さんに言われる前に患者さんの特性などを次々に当てていくと、患者さんの目が輝いてきます。
「理解してもらえた」という感動が湧いてきた心の動きを感じると、私もだんだん乗ってきて、患者さんとシンクロしてきます。
「手に取るようにわかる」状態が共感の極みです。
最後は、今どういう状態なのか、どうしてこうなったのか、特性や生育歴、遺伝的な要素などの背景と関連があるのか、できるところまで詳しく説明します。
ご本人が話したい!って思う範囲で伺っているので、滅多にありませんが、たくさん話しているうちにトラウマの蓋が開きかけてしまうことが稀にあります。そうならないようにしていますが、そうなったとしてもちゃんと責任を持ってフォローしますよ。
大変だけど、やりがいはあります。
一方で当院では少数派ですが思考がまとまらず、意思疎通が難しい方がいます。
そういう場合は、共感ではなく、単に症候・症状の評価にとどまります。
これはどの精神科医がやっても同じですね。
あれ、最初に書こうと思っていた内容からそれました。
カルテの作成が遅れるって話。
流石に2時間に及ぶ診察のカルテを診療時間内にまとめるのは困難で、後回しになります。
最近は再診1回目の時までに初診のカルテができていなかったり・・・
頭の中にエピソードが入っているうちに、他の患者さんと混同しないように書かないといけませんね。
割とインパクトのあるエピソードなので、結構細かく覚えています。
ということで、今日はもう眠いので、寝ます・・・