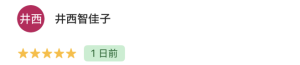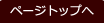政治的なことを書くことはあまり良くないかもしれません。でも、黙ってはいられません。小泉進次郎陣営によるヤラセの書き込みや高市氏への誹謗中傷の書き込みが明らかになりました。元デジタル相が指揮していたとのことです。以前権力を持ちすぎて暴走している財務省に対する批判が高まり、財務省解体デモが盛んに行われました。しかしSNSなどで財務省解体を口にした書き込みは片っ端から削除され、テレビやラジオなどのメディアも解体デモをほとんど取り上げませんでした。これらのことから国家をあげて情報統制し世論を操作していることが明らかです。医療費の問題も、偏ったデータを作り出して印象操作す、世論を誘導するなど、実際の情報操作を目の当たりにしました。北朝鮮や中国の話ではなく日本でこのようなことがいまだに行われていることに驚きます。

ブログ
インフルエンザ予防接種開始
インフルエンザ予防接種すでに開始しています。
現時点で300名ほどご予約いただいておりますが、まだまだ在庫に余裕がございます。
痛くない注射というものはありませんが、当院では「どうやったら注射の痛みが軽減できるか」
工夫を凝らして行っており、良い評判をいただいております。
また、内科に予防接種を受けに行って風邪をひいた患者さんと接触するのが気になる、という方も当院を選ばれます。
ぜひ、当院でご用命ください。
なお、精神科・心療内科の初診はいっぱいになっており、現在受付を行っておりません。
ご期待に沿えず申し訳ございません。
夏休み。
お盆は溜まった仕事をひたすらやっていたため、私個人はまだ夏休みをとっていませんでした。
少しは夏休みが欲しいと思い、9月に臨時休診を設定しました。テニスをしたり、本を読んだりして過ごすことを思い描いていました。
結果2日間は仕事から離れてすごしましたが、残りは公務やクリニックでの文書作成、審査会の準備でいつも以上に忙しい日々をすごしました。
審査会(公務)の準備はとても大変で、今日も4時間みっちり分厚い文書を読み込みました。
30分でプレゼン出来ますよ!
いつもなら前日徹夜ですが、今日は祝日で良かったとも言えます。
本題の夏休みですが、テニス合宿と題して温泉のある施設に行ってきました。テニスをしては風呂に入り、を繰り返しました。
全身黒のテニスウェアだったからか、2匹の大きなスズメバチに目をつけられてしまい、ブンブンと大きな羽音を立ててずっと頭の近くを飛んでいました。
このままではテニスができないので、「しつこいやつ嫌い!」とテニスラケットでスズメバチにスマッシュを決め、退治しました。(危険なので本当はこの対応は勧められません)
やられたら倍返し!
私はそういうやなやつです、笑。
幻滅させてしまいごめんなさい。
しかも泊まった宿も古くて、いきなり大きなゴキと遭遇。そちらも殺生、、、
もしかしてこの暑さで害虫大量発生している?
持参していった本は愛着や愛着障害に関する専門書、友人の中川教授の執筆した反芻思考に対する認知行動療法の本(反芻思考の大家から直接学ぶために留学してたんだね)、投資でお金を増やした医師の本、笑。
一冊も読めなかった、、、
私の師匠先生が愛着に関する専門家で当時はずいぶんと勉強し、開業時も愛着を主眼にして診察を行い、当院のテーマも「心の安全基地」でした。また初心にかえって学び直そうと思いました。
しかも、テニス合宿は事故だか自然渋滞かわからないけど、5時間も運転してほんと疲れたよ、、、
まあ、そんなもんだよね。
連休初日の日曜日。
最近はあまりにも忙しくて、ふとした瞬間に意識が飛ぶこと頻回で、なんとか生きています。
金曜日土曜日もふらふらになりながら診療を終え、昨夜もパソコンの前で意識失っていました、笑。
笑ってる場合でもないですが。
結局ほぼ徹夜で早朝からお出かけ。
法律に基づいた超重要な研修会に参加です。
欠席や遅刻したら国家資格を失うかもしれません。
少し早めに出発進行。
ところがどっこい、横須賀線の人身事故の影響で電車が遅延、折り返し運転だと!?
とりあえず大宮から新幹線乗って大外刈り!ギリギリセーフ!!
いざという時に力を発揮する本番に強いタイプです、笑。
会場では懐かしい先生にもお会いしたり、見覚えはあるけど「誰だっけ?」な方もいらして、、、
昼休憩にはおしゃれなカフェで
精神科医療および福祉に関連した人権や法務の研修です。
今回は医師の話より法学の先生のお話のほうが引き込まれました。
事例検討では判断に迷う難問で、大変疲れました。
人権にかかわる大変身が引きしまる内容の研修であり、その必要性を痛感しました。
こどもの診療場面では、親が受診させないとか、処方された薬を飲ませない、あるいは親が処方された薬を調整して飲ませたり飲ませなかったり。
これは法に触れる場合があり、
適切な医療を受けさせないというのは医療ネグレクトという虐待にあたります。
未成年が精神科での入院治療が必要な状態で、こどもがその必要性を理解できない場合、基本的に両親の同意が必要になります。
しかし、虐待親だった場合いろいろと難しい問題が発生します。
法律の改正で虐待親だったり疎遠でほとんど関わりがない親だった場合は、こどもの利益を判断する能力がないとして、同意保護者からは外されます。
市町村長などの首長が同意者となることができるのです。
親が治療の妨害をしてくるなど、児童相談所の一時保護が必要な場合は、家庭裁判所で親の親権停止を申し立て、児童相談所所長が親権代行者として入院の同意保護者となるという実務的な手順も確認しました。
また精神科病院での(児童福祉法に基づく)委託一時保護というものも、実際的には精神保健福祉法に定めた入院形態で実施されているということも初めて知りました。
クリニックで高度な公務を行うのは実際的には厳しいので、このような症例は多機能型診療所や病院にお願いすることになりそうです。
厚生省も多職種のいる機関を「質の高い医療を提供」と評価しており、精神科の診療報酬上も加算がとれるようになっております。
当院のように何でも院長の手の届く範囲にあり全てに関与するという小回りのきく医療機関は残念ながら国には評価されていません。
ただ、通っている方にはその良さを感じてもらえることも多く、私はそれを「質の高さ」と感じていますので、予約料を払ってでも受診する価値があると考える方に対象を絞って全力で治療に当たって参ります。
もちろん、これからもできる範囲の公務もやっていくつもりです。
9月臨時休診のお知らせ。
9月15日(月曜日祝日)から9月20日(土曜日)の週は臨時休診となります。
9月16日(火曜日)は通常通り診療を行います。
何卒よろしくお願い申し上げます。
福永先生おめでとうございます。
我が先輩の福永先生が慶應大学病院の病院長に就任されました。
呼吸器内科の教授です。
研修医の頃には科が違うにも関わらず、呼吸器科の研修医と一緒に色々教えてくださいました。
超イケメン、頭脳明晰、そして何よりコミュニケーション能力に優れ、本当にピカピカな先輩でした。
マウンティングしてくるような自己愛的な人柄でもなく、このような人間が世の中に存在するのかと驚くばかりの先輩でした。
その後もお互いに違う病院に転勤になり、神経内科の学会で私が発表したときにばったりお会いして、またまた色々アドバイスを得たというありがたミ。
あっという間に慶應の教授に就任され、
この度病院長にご就任とのこと。
このような優れた方に相応しいポジションだと思います。
おめでとうございます。
そして、われらがうっちー教授こと精神科の内田先生は副院長に就任、
岸本先生は院長補佐に就任されました。
仲間内ばかりなので、親近感がわきます。
今年の健康診断は慶應でやろうと思います。
(割引制度とかあればいいのに、、、、笑)
先日はリエちゃん(誰やねん)も慶應の血液内科教授に就任
石井くんも美容外科の最高峰、北里の形成外科、美容外科の教授に就任。
周りを見渡せば教授がいっぱい。。。
とにかくおめでとうございます。
まさか石井くんが教授になるとは夢にも思わなかったのですが、笑。
私のような人間は教授になりたいなどと一瞬でも考えたことがなかったのですが、皆様の志の高さに恐れ入ります。
ラッキーパーソン。
夜間精神科救急輪番。
有志のクリニックで夜間の精神科救急事業を支えています。
埼玉県から一応手当は出ますが(入金されているかチェックしていないけど、笑)ほぼ、ボランティアです。
保健所や精神科救急センターからの受診や、警察経由の措置入院診察などがメインの業務で、通常の診療後に居残りしてやっています。
平穏な夜であれば受診患者さんはいないこともあり、その間はずっとクリニックの仕事をしています。
どっちみち残業しないと仕事は終わらないし、大変だけど負担感はそれほどないです。
ただ、帰宅時間が遅くなるので洗濯、風呂、風呂掃除をダッシュで行わないと、寝る時間が遅くなってしまいます。
次の日の朝が怠いというのは更年期のせいかもしれません。
そんな朝、私にとってのラッキーパーソンとたまたま朝の通勤途中でばったり出会いました。
パワースポットならぬパワーパーソンです。
開業前からずっと支えてくださった方です。
お会いすると元気が出ます。
外で誰か知っている人がいるといち早く気が付きます。
相手が気がつく前にほぼ気がついています。
私の特殊能力の一つです。
ちなみに患者さんには声をかけません。
受診していることを知られたくないという方もいらっしゃるからです。
最近は私の診察を受けて喜んでくださる方も増えてきました。
ありがとうございます。
私がラッキーパーソンとなれたら良いなあ。
直接でもコメントいただけたら嬉しいです。