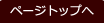コレステロールがいくつ、
血圧がいくつ、
血糖値がいくつ。
この数値の場合は、この方法で、この薬使って。
内科の先生の中にはガイドライン一直線、マニュアル一本で
基準値を目指す医療を行なっている人も少なくない。
精神科もマニュアル的な治療で統一しようという方向に向かっている。
それも大事だけど、当院では基準値を目指すことを目標とせず、その人それぞれが心地よく生きていくためにどうするかを考えていく。
その結果基準値と大きく違っていたって構わないと思う。
発達障害の過剰診断を批判する医師もいるけれど、発達障害の部分特性のために精神疾患を発症している人はとても多い。
誰にでも発達障害の特性を多かれ少なかれ認める。
いくつかその特性が重なったり、突出することで掛け算的に生活に支障をきたすことも少なくない。
だからこそ、私は細かな特性もきちんと評価する。
その結果をフィードバックすることで患者さんが自分自身を理解し、自分の上手な扱い方を習得できるようになっていく。
基準値から外れていても、お薬を使って生活が豊かになるのであれば、それでいいのでは。
薬なしで基準値の健康体でありたいという無理な理想を追求していても、ずっとつらいまま。
睡眠薬だってそう。
幼少期の虐待経験で子供の頃から夜眠れなかったという患者に、「生活習慣をちゃんとしろ」「薬なんかに頼るな」
って言い続けるのは拷問だ。脳が常に警戒している過覚醒モードを記憶しているからだ。朝の日光を浴びたって、日中運動したって、夜に入浴したって、ダメな時はダメだ。
長いことアルコール習慣がある人も、自力で睡眠を取る力や不安を軽減する自前の力が衰えてしまう。
眠れないことで脳がオーバーヒートを生じやすく、うつ病発症や認知症のリスクも上昇する。
睡眠時間に脳の中のゴミが排泄されるのに、睡眠が取れなかったら認知症の原因になるゴミも溜まりやすい。
不眠が続くことで不具合が生じやすいのは当然だ。
「睡眠衛生指導さえすれば全ての患者は眠れるようになるはずだ」というのは妄想だ。
「睡眠薬が悪だ」というのも絵空事だ。
基準値にならないといけないのではなく、基準値ではない状況を変えることができなくても快適にするにはどうしたらいいのか、
それを毎日追求している。
結果的に睡眠薬を継続することでなんとか生活を維持している人もいる。
全員が「薬なしで健やかに」という基準値になるはずだというのは机上の空論もいいところだ。