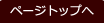研修医時代に精神薬理の大家である八木剛平先生や渡邉衡一郎先生のもと精神科のお薬について(お薬だけではもちろんありませんが)学ばせていただき、慶應大学の臨床精神薬理の研究会は25年くらいパラパラと参加させてもらっています。
そのなかで、私がとても楽しみにしているシリーズがあります。
新薬が出るたびに「◯◯(薬剤名)の全て」と題して、製薬会社を抜きにして、その薬の有用性、副作用、使い方のコツ、耐性などの問題点など丸裸にしようという企画の研究会です。
製薬会社の説明会ではなく、製薬会社の介入なしの研究会ですから、悪いことも忖度なく話題になります。
さて、今回は新薬ではなく「アタラックスP」というだいぶ古い薬です。
抗ヒスタミン薬で、蕁麻疹など抗アレルギー作用があるだけでなく、不眠や不安にも使われます。
そして、せん妄(高齢者が体調不良で入院した時に意識が混濁して悪夢を見ているような状態となり、幻視や興奮を認めます)にも効果があります。通常の抗ヒスタミン薬はせん妄にはマイナスに働くことが多いのになぜか?も議題になりました。
古い薬ですから薬価も安くて医療費がかさまずうまく使えばとてもいい。
ここ数年で古くて良い薬が厚生省の過剰な薬価引き下げによって製薬会社が適当な理由をつけて生産をやめてしまいます。
高価な新薬をバンバン売って利益を出したいからです。医療費は当然高くなります。
厚生省もそういう視点でちゃんと考えてほしいですね。
安くて良いものを残すことも考えて、古くて良い薬の薬価を赤字が出ないように薬価を調整する必要があります。
新しくて高い薬が皆様に合うとは限らないのです。
当院ではそれぞれの方にどの薬が合うのか、よーく考えて治療を行っています。
どの方にも同じセットを処方するということは行っていません。
精神科の治療ってクリエイティブな作業だと思っています。
マニュアルはあっても誰一人同じではないし、個別性をどう理解するか大事なことです。
もちろん共通性を見出すほうが基本になりますが。
私にとっては全身全霊で私の命を搾り出して創造するアートのような感覚で治療を行っています。
その人の生活や症状がありありとイメージできるようにお話を伺い、治療を組み立てる。
どうしてそうなっているのか、そこを紐解き、それに対する対応をケースバイケースで創造する。
大変だけど、天職だったかなと今は思っています。
今度から職業クリエイターと名乗っていいですか?笑