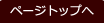下品な表題で失礼いたしまする。
開業以来ずっとこんなくだらないブログを書き続けているメンタルクリニックも珍しいのではないでしょうか?
どういうわけか、このブログをご覧になって受診される方も少なくありません。
「ブログ見て来ました!」って言われると、嬉しい一方、顔から火が出るほど恥ずかしい気持ちになります。
医療情報に限らず、私の暴言も書き殴る。
眠気に耐えられなくなるまで書いて、
校正せずに途中でもとりあえずそのままアップする。
そんなスタイルでやって来ました。
校正して、きちんとした文章にしてから公開していたら、ほとんど更新できなかったでしょう。
そんな暇、ありません。
ブログ以外のホームページの本文については、最初は真面目に真面目にしっかりした内容を吟味して作文しました。
一部業者さんが用意してくれた文章を使っている部分もありますが、疾患の説明などは厚生省などが公表しているものをそのまま使うのではなく、私のオリジナルの解釈も織り込んだ内容となっております。その違いに気がついた方が受診してくださったりしました。
10年以上経ってアップデートすべきところもありますが、先延ばしになっています。
その他診察の案内など横浜の先輩のホームページを参考にさせていただきました。
先輩から拝借した文言以外は、できるだけ自分の考え出した表現を使い、他のHPとは違うものを作ろうと頑張りました。
しばらくすると、私の独自の文章の一部がそのままさいたま市のクリニックのHPに載っているのを発見。
最初は自分のH Pを見ているのかと錯覚しました。面識がないわけではないので、一言言ってくれればいいのにと思いました。
その後も新しいクリニックのHPに私の言葉が・・・
また精神科病院のHPがリニューアルしたと思ったら、また私の表現が・・・
みんな結構普通にパクるんだな、と感心しました、笑。
でも、模倣されるということは、彼らに響くものがあったということなのでしょう。
それは誇らしいことでもあります。
ただ、私のHPが陳腐になってしまったので、また他人とはちょっと違うものを作ろうかと思いましたが、
もうどうでもいいか?笑。