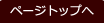まず最初に自分のことを弘法って言っちゃってることをお許しください、笑。
一般論として、本当にできる方は「自分が有能だ」と言ったり、あるいは相手にそう思わせるように強くアピールすることはありません。もっと謙虚です。
「バカほど自己評価が高い」そういう現象をダニングクルーガー効果と言います。
ただ、私のブログでは極端に謙遜した表現はしないようにしています。謙遜を真に受けられてしまうと何の取り柄もないクリニックだと思われてしまうかもしれません。ありのままをお伝えしますので、そのまんま受け取っていただけると良いように工夫を凝らしております。
良い悪いではなく、冗談が通じる方、通じない方、皆様いろいろですから。
今回、弘法とうぬぼれた内容は、採血の技術に関してです。
今や採血や注射を自分でやっている医師は多くないかもしれません。
だいたい看護師さんがやってくれるものです。
総合病院や大学病院では、若い看護師さんが最初に採血をして、失敗すると中堅、ベテランと呼ばれていき選手交代します。お年を召されていなければ師長さんが出てくることもあるかもしれません。どんなベテランの看護師でもうまくいかない場合は、医師が呼ばれます。私が若い頃は点滴に関しては基本医師が行うものでしたが、最近は看護師さんがまずはやってくれるようになりました。点滴も看護師さんがうまく入れられないケースは医師が呼ばれます。
というわけで、医師が採血するときはいわゆる採血困難者の採血を行う場面でした。
昼間の明るい時間帯ならまだしも、夜中の2時、3時に薄暗い病室の中で、狭いベッドサイドで、すでに点滴が漏れてしまって青あざだらけ、腕がむくんでいて血管も見えない状況、ご老人の硬くて細くすぐに破れてしまう脆弱な血管を探し出して点滴など行うのは非常に難易度が高いものでした。ひどい時は朝方まで格闘して、手の甲や足の甲だけではなく、首の表面の血管や頭のこめかみの血管をつかって点滴することさえもありました。
さらに私は新生児室(NICU)での採血や点滴のトレーニングも受けており、最も困難な相手から血を抜き取ったり、注射をすることができるようになりました。せっかくの技術を維持したいと思い、(勤務医時代は看護師さんに任せていましたが)開業と同時に全て自ら行うことにしたのです。
その結果、「私はベテランの看護師さんでも採血ができない採血困難者です」と名乗る患者さんも一撃必殺でサクッと採血して差し上げる場面が繰り返され、患者さんにはよく驚かれるものでした。
そんな私なので、今回も「なんや、こんなの簡単や」と豪語し採血したのです。
血管の太さや走行、弾力性、皮下脂肪のなかでの固定性、流動性などさわりながら評価します。
さらに、その方がどのような性格発達特性か散々問診した後なので、たとえば感覚過敏が目立って、恐怖心が強い患者さんならば、針を刺した途端血管がキュッとしまって逃げるということも想定されます。大体の場合は横に逃げるので、逃げ場を計算して追い詰めた先で針が血管に刺さるようにすればほぼ間違いなく採血できます。
採血を異常に怖がる方は自閉スペクトラム症の特性が認められることが多いです。失神してしまう方はベッドで寝ていただき採血します。ありとあらゆることを想定して確実に採血する方法を評価し、実施します。
ところが今回の患者さんは血管のさらに下に皮下脂肪組織が厚めに広がっっており、横の動きを抑えたつもりだったのが、血管が下に潜り込んで逃げてしまったのです。結果、血管にかすりもせず、採血に失敗。それに気がついて反対の腕では下に潜り込む血管を下に向けて追い込んで採血に成功しました。
1回採血に失敗してしまい、患者さんに謝って許していただいたので、2回目のチャンスが得られ、結果として成功したのでなんとか検査を実施できました。患者さんには申し訳ないけれど、勉強になりました。下に逃げるケース!もう失敗しませんよ!
私、失敗しませんから、と言ってみたいもんですね。